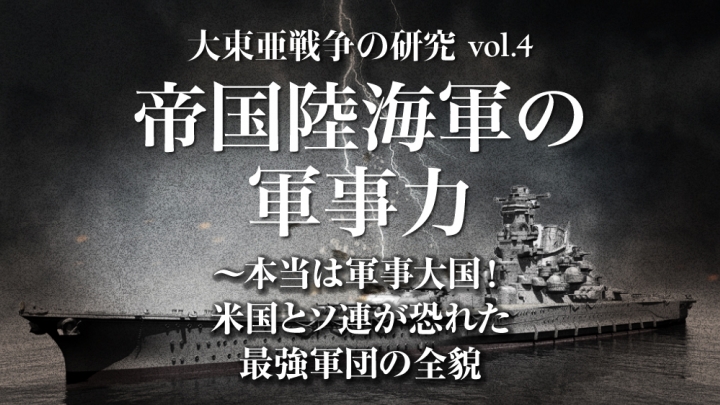
大東亜戦争の研究 vol.4 帝国陸海軍の軍事力〜本当は軍事大国!米国とソ連が恐れた最強軍団の全貌
¥29,800 (税込¥32,780)
ご購入日より1ヶ月以内であれば、ご解約の上返金を承ります。
※過去にご購入された方は返金保証の対象外となります。
幕末からわずか数十年で、日本は「近代国家の軍と産業」をそろえ、列強と真正面から向き合いました。無茶な賭けではなく、準備と選択の積み重ねです。なぜ、そんな短期間で実現できたのか?
薩長を軸に陸軍は再編され、士官学校で人材を育成。西南戦争の教訓は、近代的な指揮・補給の「型」をつくりました。徴兵令は負担でもあった一方、「国を守る力を全国で持つ」という合意づくりでもあったのではないか。
海軍は長崎海軍伝習所などで学び、連合艦隊として動く訓練を重ね、国産の建艦と技術で底力を高めます。日清戦争で勝利しても、三国干渉で「勝っても孤独」を痛感。日露戦争では日本海海戦の勝利、火薬・信管などの技術、対外PRで世界に存在感を示しました。
ただし成功は同時に“型”を固定します。艦隊決戦へのこだわり、資源や補給の弱さ、同盟・貿易に依存する体質――これらは長期戦で不利に働く伏線になりました。ワシントン会議の軍縮は焦りを生み、やがて大和・零戦・空母機動部隊という「日本流の解」へ。開戦初期は強かったのに、なぜ持久戦で失速したのか?
日本は「学ぶ・まねる・工夫する」で一気に強くなりました。では、どの判断が長期戦の壁を生み、どの思い込みが視野を狭めたのか。技術、兵站(補給)、外交、世論――それぞれの歯車がどこでずれたのかを丁寧に追います。
答えは、この講座で。
