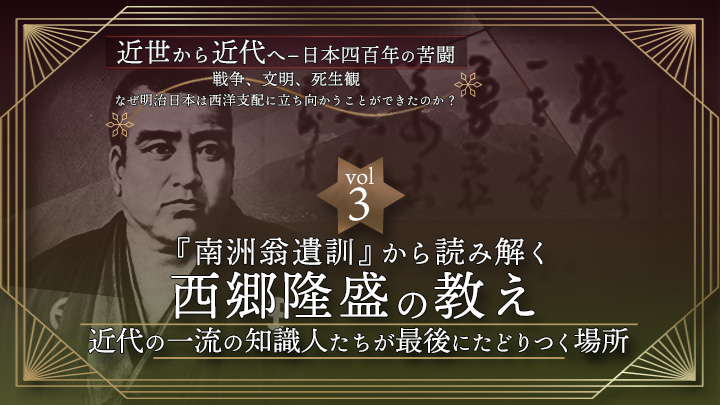
近世から近代へー日本四百年の苦闘 ~戦争、文明、死生観ーなぜ明治日本は西洋支配に立ち向かうことができたのか? vol.3 『南洲翁遺訓』から読み解く西郷隆盛の教え〜近代の一流の知識人たちが最後にたどりつく場所
¥29,800 (税込¥32,780)
ご購入日より1ヶ月以内であれば、ご解約の上返金を承ります。
※過去にご購入された方は返金保証の対象外となります。
あなたは知っていますか?
戦後、日本について真剣に考える一流の知識人たちが、その生涯の果てに決まってたどり着くのが、「西郷隆盛」なんです。
三島由紀夫は自決の2年前に「銅像との対話—西郷隆盛」という一文を書きました。 また、その三島の自決に冷淡な評価をしていた江藤淳も、不思議なことに、のちに『南洲残影』を書き、しばらくして自殺しました。 代表的な皇国史観の歴史家である平泉澄の最後の著書も、『首丘の人・大西郷』です。 日本の神道家、葦津珍彦(あしづうずひこ)も六十歳代半ばにこんなことを書いています。 「生きて西郷ほどの人物を師として、その師とともに…その生涯を燃やし尽くした戦没者に対して、羨望の情禁じ難い」(『永遠の維新者』) それだけ、西郷隆盛には底知れぬ、日本人にとって何か大切なものを秘めた、奥深さがあるようです… 文芸評論家・林房雄も生涯ずっと西郷隆盛にこだわりました。 なぜか?
まずその大前提として、林房雄は先の大戦について著書『大東亜戦争肯定論』でこう書いています。「この百年間、日本は戦闘に勝っても戦争に勝ったことは一度もなかった」
つまり、彼が言いたかったことは、「日本は一貫して勝てなかった。日本の論理をちゃんと明示することができなかった痛切な百年間であった」ということです。 その裏返しが、西郷隆盛へのこだわりとなって表れました。 つまり、当然、戦後の日本のあり方に批判的ではありますが、同じ理由で戦前の日本も批判的なんです。
なぜなら、そこに「日本がどうあるべきか」という観点が欠けているからです。 日本近代史というのは、その過激な西欧化の道行の中に、日本人の「生き方」を見失っていく過程でありました。 鹿鳴館に象徴されるように、文明開化と同時に西洋に媚びる日本人が増えました。
それと同時に一方で、日本人が西欧人になりきれないことへのルサンチマンを溜め込んでいく歴史でもあったのです… ペリーが日本にやってきてから、幕末の日本人はかつてないほど巨大な危機感を抱きました。 このままでは外国に支配されてしまう、近代に支配されてしまう… そんな危機感の中で「俺たちとはいったい何者なのか」という自己の内面を見つめる必要がありました。
「日本人は何者なのか」… それを一番体現していたのが西郷隆盛でした。 あえて語弊を恐れずにいうと、、、 明治政府は幕藩政治に染まり、、、 特定の人間が政治を牛耳っていく状態になる、、、 そんな姿を見て、西郷隆盛は、自分で作った明治政府を自分で見限って、「第二の維新」を唱え、「維新の精神」をもう一度取り戻そうとする… それが最期、西南戦争で反政府の〝賊軍〟にまわって死んでいく西郷隆盛の生涯でした。
そういう西郷隆盛の姿を、葦津珍彦は「永遠の維新者」と呼びました… 西郷隆盛こそ、2000年来の伝統を持つ、〝日本人そのもの〟だったわけです。 ですから、西郷隆盛を知ることは、2000年来の伝統を持つ日本そのものを知ることになります。
皇學館大学で平成8年からずっと、週に一度、放課後に自由参加の勉強会で、西郷隆盛の〝唯一の著書〟『南洲翁遺訓』を学生と読み、講義を続けている松浦光修先生に、ご解説いただきます。
