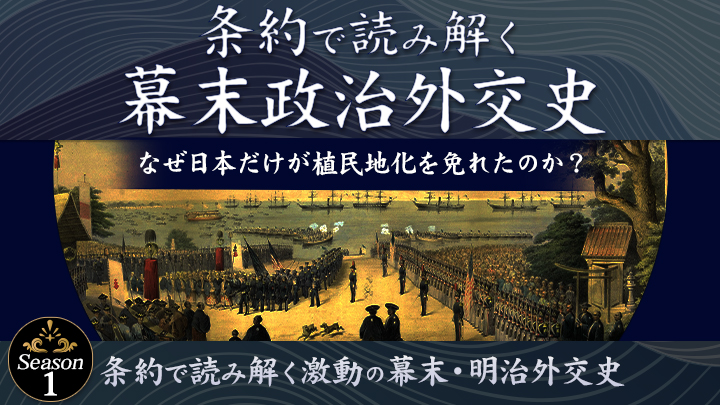
vol.1 条約で読み解く幕末政治外交史〜なぜ日本だけが植民地化を免れたのか?
¥29,800 (税込¥32,780)
ご購入日より1ヶ月以内であれば、ご解約の上返金を承ります。
※過去にご購入された方は返金保証の対象外となります。
日米和親条約ひとつをとっても、あえて誤訳説が生まれるような文言に調整するという、高度な日本の外交交渉を行っていたのです。幕末日本は「極東の未開の小国」というイメージで語られがちですが、全然そんなことはありませんでした。
いまお話しした「第11条問題」を見てもわかるように、日本語の条文の「兩國政府」というわずか4文字の裏には壮絶なドラマがありました。このように幕末以来、いかに欧米列強に支配されずに、力のない日本が独立を守っていくか、というギリギリの決断を下した、日本人の英断、勇姿が、外交・条約を読み解くことで見えてくるのです。
日本は国際法に精通していたからこそ、欧米列強の植民地にならずに、アジアで唯一独立を守り続けてこられたのです。苛烈な帝国主義の時代とはいえ、白人諸国はいきなり力ずくで侵略しに来るわけではありません。
「外交」「条約」を通して合法的に侵略しているのです。元々、寒冷地帯で食事が不味く、暮らしが貧相だった西欧人は、香辛料や陶磁器、絹などを求めてアジアにやってきました。始まりは貿易という外交事務上の問題でした。当初は事務的な外交上の手続きであっても、条約がわからない国は、相手の国に不信感を与えたり、約束を守れずに相手を怒らせたり、あるいは相手が悪意のある国なら、騙されることだってあるのです。
それがだんだんエスカレートして、スペイン人やポルトガル人たちは南米に攻め込んで、インカ帝国といった現地人の文明を滅ぼし、金銀宝石を根こそぎ奪っていきました。南米の現地人やアフリカ人を捕まえて、奴隷としてヨーロッパに連れ帰ったり、植民地の農場で働かせたりしました。日本の近くではベトナムや中国といった国が次々と、イギリスやフランスに侵略されました。このような例はあげればキリがありませんが、いまここで西洋諸国の残虐な行為を非難したいわけではありません。
こういう現実の荒波に向かって、私たちのひいおじいさん、ひいひいおじいさんたちは漕ぎ出していかなくてはならなかったということです。日本が植民地にされなかったということは、こういう残虐な相手に対しても「対等に」交渉できていたということです。
しかし、学校の教科書ではこのような外交の裏にあったドラマまで教えてくれるほど親切ではありませんし、そもそも、日本史は戦後GHQによって改ざんされ、消されているので、余計に何が起こっているのかわからなくなっているのが現状です。しかし、どれだけGHQが教科書を書き換え、歴史学者を洗脳し、マスコミが自虐史観を拡散しても、外交文書や条約を書き換えることはできません。
そこにこそ、歴史のドラマ、日本人の物語、緊迫した時代の空気が隠されているのではないでしょうか?
文芸評論家の林房雄は「大東亜戦争は百年戦争の終曲であった」と言いました。あいだに5年か10年ずつの「平和」があっても、それは次の戦闘のための小休止にすぎなかったというのです。 ではいつ始まったのか?
日本近海に外国船が出没し出した江戸後期からだと言います。 実際、日本の降伏文書署名式が行われた1945年9月2日、東京湾に浮かぶ戦艦ミズーリには、あえてわざわざ31星の「星条旗」が本国の博物館から持ち込まれました。
なぜ31星の星条旗なのか? これは当時はまだアメリカに31の州しかなかったペリー艦隊に掲げられていたものなのです… これをわざわざ敗戦した日本に示すとは、つまりこういうことです。
「アメリカがこの旗を掲げて文明を教えたことを忘れて日本は戦端を開いた。そのことを後悔し反省しろ」 アメリカこそ、大東亜戦争が幕末からの百年戦争であったことを強く意識しているのです。 大東亜戦争はまぎれもなく、幕末から続く、欧米列強との独立をかけた戦いの延長線上にありました。
つまり、大東亜戦争を正しく理解するためには、幕末からどんな外交交渉が行われ、どんな物語があったのかを知る必要があるのです。
そこで産経新聞「正論」元編集長の上島嘉郎さんと制作したのが『条約で読み解く幕末政治外交史〜なぜ日本だけが植民地化を免れたのか?』です。
教科書には描かれていない外交交渉と、その裏にある幕末日本人の物語を紐解くと、そこには独立を守り、理想の社会を築き上げるための壮絶な列強との戦いがあったことがわかります…
